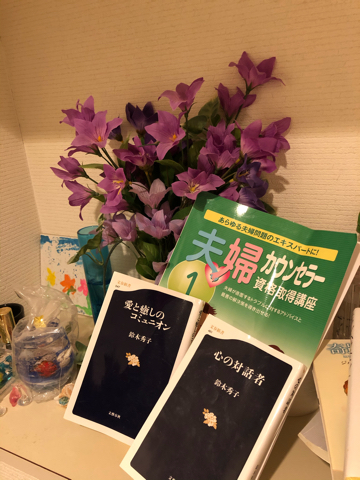
 いつも読んでいただき,ありがとうございます!
いつも読んでいただき,ありがとうございます!
遂に弁護士木下は「夫婦カウンセラー」資格を取得しました~(パチパチ!)
法律専門職として最難関の「司法試験」に合格すれば,それ以上何の資格がいるのか・・と以前は傲慢に思っていた私。
でも,離婚,面会交流などの家庭問題を多く取り扱う中で,それだけでは,本当の意味での解決にならない・・・と分かってきました。
一方で,カウンセラーの資格を取る前から,
「先生は,法律のことだけでなく,カウンセリング的な知識もあってありがたい」
と言われることも多くありました。
これまで法的な問題でない場合,
「カウンセラー」さんを紹介することもありましたが,
「弁護士の先生の方が守秘義務もしっかりしているから安心できる」
「カウンセラーさんではなく,弁護士である先生の意見を聞きたい」
と言われることもありました。
ご相談者から「カウンセリング」として面談を依頼されることも多くなりました。
そこで,「カウンセリング力」って何だろう・・
と改めて勉強したいと思い,書籍を読んだり,資格の勉強をしたりする中で気づいた
「相手の問題解決力」を引き出す「聴く力」について今回はシェアします。
今回読んだ書籍「愛と癒しのコミュニオン」
「心の対話者」(いずれも人文科学研究科博士鈴木秀子著)は,
以前にこちらでご紹介した元家庭裁判所調査官,
飯田邦男元家裁調査官が「話の聴き方」を学べる本,
「アクティブリスニングの教科書として書かれた内容で,福祉的視点も学べる」本としてご紹介してもらったものです。
この内容を知ることで,話す相手が自分で気づいて,問題を解決するための「聴き方」「話し方」のコツが分かります。
子育てをしていて,子供がどうしたら自分で進んでやってくれるのだろう・・・という時にも私自身はとても役に立ちました!
そして,相手が話したくなくなり,問題解決も出来なくなるダメな「聴き方」,コミュニケーションをなぜ私たちはしがちなのか,
それを避けるにはどうしたらいいのか,も分かります。
さらに,「聴く力」を高めると,人間の唯一の根源的欲求を満たすことができ,
相手との関係を深め,相手を本当の意味で勇気づけられることを知って感動しました!
弁護士の仕事って,考えてみれば,代わりに相手の問題を解決する,のではなくて,
問題を解決しようとするその方ご本人の解決をサポートをする仕事・・・
そのためには,
ご依頼者,ご相談者の中にある「問題解決力」を引き出すことが大切!
そして,依頼者,ご相談者との関係を深め,勇気づけられる力を付けられたら・・
一緒にこれから困難を乗り越えていく上でとても心強い!
子供の悩みや課題解決をサポートするお父さん,お母さん,
依頼者,ご相談者の話を聞いて,悩み,課題を解決するサポートしていらっしゃる方には,ぜひ知って欲しい!と思いましたので,お伝えしたいと思います。
なぜ「上からものをいう」態度になるのか~聞くモードになるコツ
カウンセリングの重要ポイント~同情と共感の違いとは?
人間の唯一の根源的欲求とは何か~自分らしく生きるコツとは?
をお伝えします♪
1 なぜ,上からものをいう態度になる?
よくあるパターンの会話。
A「これだけ頑張っても業績が上がらないと,はっきり言って厳しいよ」
B「そりゃ,仕事っていうのは厳しいもんだよ。弱音を吐く前に足で稼ぐしかないんだよ」
・・・これは職場にありがちな良くないコミュニケーション。
このような「聴き方」「話し方」をされれば,Aさんは屈辱的な気分を味わって「こんな奴に話すんじゃなかった」という後悔の念だけが残り,信頼関係は崩壊する・・
このようないわゆる「上からものをいう」応答は,なぜおこるのでしょうか・・・?
書籍「心の対話者」によると,
それは,聴き手の「自分が正しいと思っている方向に行きたい」という願望にある,とのこと。
その背後には,「自分には正しいことが分かっている」という思い込みがある。
特に私たち弁護士の様に「相談を受ける立場」になると,
相手より自分の方が物が分かっているという優越感,上下意識があるため,
「上からものをいう姿勢を鮮明にする傾向がある」とか・・・
耳の痛い話です・・・
聞くより前に話したがる・・という典型ですね・・
うちの事務所の場合,他の弁護士に相談して,このような「上から目線」を感じ,
たどり着いて来てくださる方も多いのですが,改めて注意したい点だと思いました~
このパターンを直し,「聞くモード」になるためのコツは,
「否定も肯定もせずに聞く」ということ,とのこと。
これは以前,コンサルタントの勉強をしたときに師匠が言っていた「素直」という「考え方」と同じ。
「私も同じ意見です!(肯定)」という必要はないし,
「それは違います!(否定)」する必要もない。
「あなたは,○○と思うのですね・・・」と相手の考え方を相手の考えとしてそのまま受容すること。
これを意識していたから,今までも自然とアクティブリスニング,カウンセリングの基本となる聴き方もこれまでも出来ていたのかな・・と思いました。
みなさんは「上からものをいう」態度でお話を聞いていませんか?
~私も改めて,「聞くモード」を意識したいと思います。
2 同情と共感の違い
夫婦間セラーの資格を取るための教材にあったカウンセリング重要ポイントの一つ
「同情ではなく共感すること」
では,「同情」と「共感」の違いって何でしょうか・・?
この2つは,
「他人の感情をその身になって感じる」という点では非常に似ていますが,
解説によると大きな違いは2つ。
①共感は,同情のように苦悩や不幸というネガティブな感情のみでなく,喜び,悲しみという全ての感情を共に感じる
②共感は,ただ感じるだけでなく,相手の状況や立場を「理解する」
「同情」では,相手の劣悪な環境や苦しみにもらい泣きをするような感じのため,相手の感情に飲み込まれてしまいがち。
でも,カウンセラーは,相談者の問題を解決するために,感情に飲み込まれるのではなく,共に感情を共有しながら,相談者のことをより深く理解する「共感」が大事。
具体的には,相談をされたときの反応が・・・
「あなたはなんてかわいそうなのでしょう。そんな状況では気持ちも滅入ってしまいますよね」・・同情
「本当におつらい状況なのですね。○○ということで,その大変さやつらさを誰も理解してくれていない,と感じていらっしゃるのですね」・・共感
やはり,ここでも,「否定も肯定もせずに聞く」というスキルと同様に,
自分の意見,感情とごちゃ混ぜにせず,事実を確認した上で,
「あなたは,このように感じていらっしゃるのですね」と少し離れて,理解,受容を示すことがポイントかな,と思いました。
そして何よりも,カウンセリング,相談の目的である
「問題を解決する」という意識が大切で,
そのためにどのような聴き方,応答をしたらいいのかを考えることが大事だと思いました~
もっとも,間違えると,あくまで,弁護士である私が何とか解決してやろう!と気負いすぎてしまいそうですが・・・,
ご相談者がもともと持っている問題解決力を引き出すためのサポートをする,という意識も大切にしていきたいと思いました~
みなさんは,同情と共感の違い,知っていましたか?
問題解決力を引き出す「共感」力,磨いていますか?
3 人間の唯一の根源的欲求~自分らしく生きるコツ
人間誰もが持つ唯一の根源的欲求って何でしょうか・・・?
「愛と癒しのコミュニオン」の著書の中で,このように紹介されていました。
それは・・・
「自分の存在が他者から理解され,認められ,受け入れられ,出来れば高く評価され,大切にされたい。」と同時に,
「自分自身もまた自分が良い人間と思えるような,他の人に役立つ存在でありたいという希求」。
「聴く力」を高めたら,この根源的欲求の大きな部分を満たせるのではないかな,と思いました。
「大切にされている」「自分は良い人間」「役に立つ人間」と感じるのは,
その人本人の気持ちだから,直接変えることはできないかもしれないけれど・・・
直ぐにこちらの意見を話したりせず,
相手の話を「共感」して聴く,ということが出来れば,
相手は自分のことを「理解され,認められ,受け入れられた」と感じることが出来ると思いました。
そうすることで,自分は大切にされている,自分は役立つ人間だ,と思える大きな一歩になることをこの本から教えてもらいました。
自分の根源的欲求を満たしてくれたら・・・
その人(聴き手)を心から信頼できると思いますし,その人と一緒に頑張りたい,と思えますね!
なので,「聴き方」のスキルを高めることはもちろん大切なのだけれど・・・
どうしたら,この人が受け入れられていると感じてくれるだろうか,大切にされていると思ってくれるだろうか・・・
という「考え方」をいつも忘れないようにしたいと思いました~
みなさんは,人間の唯一の根源的欲求を知っていましたか?
話す相手,大切な家族の根源的欲求を満たすコミュニケーション,していますか?
まとめ 相談者には問題解決力がある
弁護士になって20年目になりますが・・・
最初のころはずっと,弁護士のところに相談に来るんだから,
何らかのアドバイスを授けないといけないと思っていた・・・
なのに,なぜこの人はしゃべり続けて,こちらの話を聞こうとはしないんだろう?と思ったことも何度もあった。
けど,10年たったころから(遅いけど),気がついたことがあった。
弁護士が問題を解決できるなんて,思い上がりかも・・と。
本当は,相談者ご自身がどうやって問題解決をしていったら良いのかは分かってる。
ただ,混乱していて,その解決方法に気づいていないから,整理したくて話しているのではないかな。。と。
法律的な知識,解決方法が聞きたい場合もあると思うし,そういう質問があれば,もちろん答えるけれど,どちらかというと,そういうことが聞きたい場合は少ない気がする。
なので,法的な質問がない限りは,問題解決の力を引き出すためにサポートできたらいいなあ・・と。
そう思ったら,相談時の対応の仕方もすごく変わってきたと思う。
目の前のご相談者を尊敬し,問題解決力ある,と思って対応する・・それを今は意識しています。
離婚調停を起こされたけれど離婚したくない,という方の相談も増える中で・・
他の事務所では,「そのような場合,弁護士に出来ることはない」「離婚を決めて,有利な条件を引き出すため,ということなら引き受けるけれど,離婚したくない方については引き受けられない」
と言われ,うちの事務所にたどり着く方も沢山見てきた・・
「弁護士」として出来ること,と考えると限界があるかもしれないけれど,
私はそういう方であってもサポートしていきたいと思っているので,
カウンセリングの力,傾聴,アクティブリスニングの力を磨くようにしました。
書籍を紹介して下さった飯田先生が下さった言葉。
「弁護士の方は話を聴くのが仕事ですので、皆さんそれぞれ勉強されているものと思いますが、それでも傾聴やアクティブリスニングについて意識して学んでいる人と、
そうでない人では、次第に差が生まれるものと思います。学習を継続していると、
スキルや方法だけでなく、その姿勢や雰囲気が身に付きます。これらは、依頼人や当事者に次第に感じてもらえるものと思います。」
この言葉を大切にして,これからも学び続け,安心感をもってできる相談,大切にされていると感じる相談対応,雰囲気をこれからも事務所全体として,大事にしていきたいと思います~
医療の専門的知識を持つ医師でも,
「ぶっきらぼうで怖いな~」と思う先生に私自身出会い,話しづらいな,と思うことも少なくない。
専門的知識,スキルはもちろん大切だけれど,
その人の持っている力が最大限に発揮されるよう,
そして問題の根幹を見落とさないよう
ご相談者が話しやすく,課題を解決することにつながる
「聴き方」をこれからも意識していきたいと思います!
これを家庭でも実践すると,旦那さん,奥さん,
そして子どもたちが安心して話すことが出来て,
自分で課題を解決するための方法に気づいて,
行動してくれるのも実感しているので,
家庭内や職場内での実践もお勧めです!
それでは,このブログが読んで下さったみなさまが,「聴く力」を上げることで,相手との関係性をより良いものとし,課題を自分で進んで解決するサポートをするためのヒントとなりますように。
そして,職場,家庭内で「根源的欲求」を満たすコミュニケーションがあふれ,お互いの「考え方」を認めあえる文化が広まっていきますように。
家庭生活の平穏,仕事で成果を出すためにも,この夫婦関係,親子関係,人間関係を円滑にするための研究をこれからも続けていきたいと思います!
これからも,親子,夫婦関係にとって大切なこと,心を癒すスキル,「話し方」「伝え方」「聴き方」のスキル,考え方を磨いていきます!!
今回も最後まで読んで下さって,ありがとうございました!